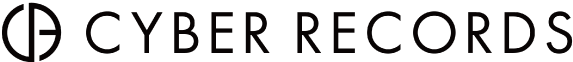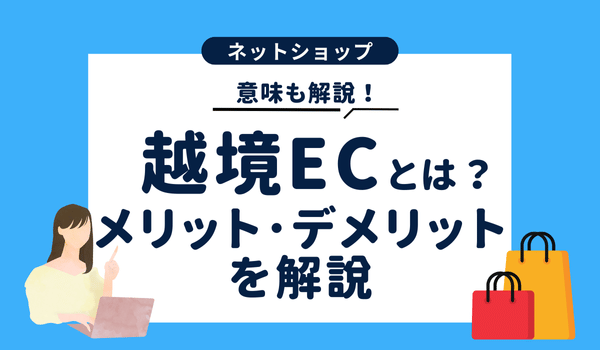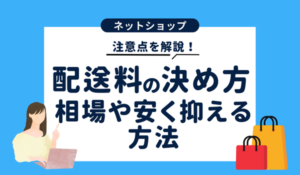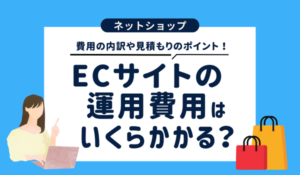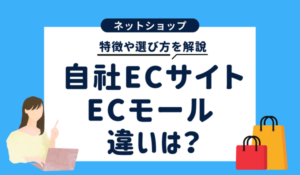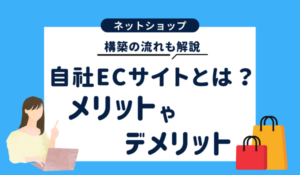国内EC市場の成長に限りを感じ、海外への販路拡大を検討していませんか?
しかし「越境EC」と聞いても、言語や物流の壁など不安が多く、「何から手を付ければよいかわからない…」そんな悩みを抱える方も多いでしょう。
実際、越境EC市場は年々拡大しており、今や多くの日本企業が海外進出で成果を上げ始めています。
本記事では、越境ECとは何か、そのメリット・デメリットから始め方のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。
記事を読むことで、海外市場への一歩を踏み出すための具体的な知識と戦略を得られるでしょう。
越境ECに興味がある方、これから始めようと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
越境ECとは?

越境ECとは、インターネットを介して海外の顧客に商品やサービスを販売する仕組みを指します。
文字通り「国境を越えたEC(電子商取引)」で、国内ECの枠を超えたグローバル市場への参入手段です。
具体的には、自社のオンラインショップや海外モールに出店して、言語や決済通貨、物流オプションなどを海外仕様に対応させることで海外ユーザーに商品を届けます。
国内ECとの相違点として、国や地域によって異なる法律・商習慣・配送手段などを考慮する必要がある点が挙げられます。
需要の高い海外市場をうまく開拓すれば、売上アップやブランド力強化につなげられますが、準備不足だとトラブルに巻き込まれやすいのも特徴です。
まずは越境ECの概要を正しく理解し、メリット・デメリットを把握することが成功への第一歩です。
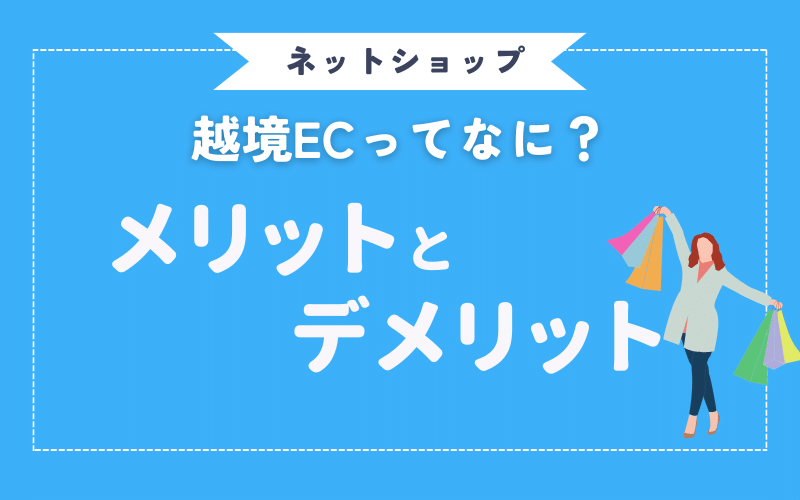
越境ECが注目される背景と市場動向
近年、インターネット環境の整備や国際物流の発達により、海外から商品を購入するハードルが大幅に下がっています。
そうした世界的な潮流の中で、越境ECは日本企業にとって新たな売上源およびブランド価値向上のチャンスとして注目されています。
国内市場の少子高齢化や競合激化を背景に、海外市場へ活路を見出す動きが加速しているのが現状です。
背景1:世界的なEC市場の拡大
国際的にインターネットショッピングの需要が年々増加しており、経済産業省の調査でも越境ECが世界規模で急成長していることが報告されています。
スマートフォンの普及や物流ネットワークの充実により、海外製品を気軽に購入できる時代となりました。
こうしたインフラ要素が整備されたことで、越境ECを利用するユーザーも増え、グローバル規模でのオンライン売買がより活発化しています。
背景2:インバウンド需要の波及効果
訪日外国人が増加する中、日本で買い物した商品のリピート購入を越境ECで行うケースが増えています。
旅行中に気に入った商品や、日本特有のサービスに魅力を感じた外国人観光客が、帰国後もオンラインで継続的に購入できる仕組みは企業にとって大きなビジネスチャンスとなります。
特に化粧品やアニメ関連商品、食品などは「Made in Japan」の信頼性が高く、越境ECで売上を伸ばしやすい分野と言えるでしょう。
背景3:国内市場の伸び悩みと海外へのシフト
日本国内では少子高齢化が進み、EC市場自体の成長率が徐々に鈍化する懸念があります。
これに対して、海外のEC市場は依然として旺盛な消費需要を抱えており、成長余地も大きいです。
国内だけに依存せず海外販路を開拓することで、売上を安定させる戦略として越境ECがますます注目されています。
市場動向:アジア圏・北米圏を中心に拡大
越境ECの利用者が特に多いのは、中国や韓国、東南アジア諸国などのアジア圏とアメリカを中心とした北米圏です。
中国では国を挙げてEC関連インフラやキャッシュレス決済を推進しており、Tmall GlobalやJD Worldwideなどの大手プラットフォームが市場を牽引しています。
北米市場ではAmazonやeBayが圧倒的な存在感を持ち、日本企業が参入しやすい環境が整いつつあります。
こうした主要市場を中心に、世界のEC利用者総数は今後も増え続けると予想されており、越境ECに乗り出すチャンスも拡大していく見通しです。
企業が海外ユーザーのニーズを的確に捉えれば、国内では停滞気味の売上を大幅に上積みできる可能性があります。
越境ECの種類・モデル
越境ECを運営するにあたっては、大きく分けて「モール型」と「自社サイト型」の2種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の経営資源や販売戦略に合った方法を選ぶことが大切です。
それぞれの特徴やメリット・デメリットについて順番に解説していきます。
モール型越境EC
モール型は、海外向けのECモール(Amazonグローバル、eBay、Tmall Globalなど)に出店して販売するモデルです。
既存のプラットフォームを利用するため、集客力や決済システムが整備されており、比較的スピーディーに越境ECを開始しやすいメリットがあります。
一方、出店料や手数料が発生し、モール内の規約に従う必要があるため、販売戦略の自由度が制限される場合もあります。
また、同じプラットフォーム上には競合他社も多数存在するため、価格競争に巻き込まれやすい点には注意が必要です。
自社サイト型越境EC
自社のドメインやECサイトで海外向けに販売するモデルです。
ShopifyやMagentoのような多言語対応のEC構築サービスを利用すれば、海外決済やローカライズ機能を実装しやすいのが特徴です。
サイトデザインやブランディングを自由に行えるため、自社の世界観をアピールしやすく、顧客データの蓄積やリピーター施策にも取り組みやすい反面、マーケティングや集客は自力で行わなければなりません。
海外SEO対策、SNS活用など手間やコストもかかるため、リソース配分が成功のカギを握ります。

越境ECのメリット

越境ECには、国内ECのみでは得られないさまざまなメリットがあります。
越境ECの主なメリットは以下になります。
- 海外需要の取り込みによる売上拡大
- 実店舗出店に比べて低コストでの海外進出
- 為替差益や輸出優遇による利益増の可能性
- 国内市場依存リスクの分散
世界を舞台にすることで新しいチャンスが生まれる一方、正しい戦略を立てることで効率的な拡大も期待できます。
それぞれのメリットについて、順番に解説していきます。
海外需要の取り込みによる売上拡大
日本国内だけでなく、北米や欧州、アジアなど幅広い地域に商品を販売できるため、潜在的な顧客数は飛躍的に増えます。
独自性のある商品や、高品質な日本製品への需要がある場合には、海外のファンが根強くつく可能性が高まるでしょう。
実店舗出店に比べて低コストでの海外進出
リアル店舗を海外で構えるには、現地のテナント契約や人件費など大きな投資が必要です。
一方、オンライン中心の越境ECは、プラットフォーム利用料やシステム構築費こそかかるものの、物理的な初期投資が少なくて済みます。
小規模から始めて徐々に拡大することも可能です。
為替差益などによる利益増の可能性
海外での売上を外貨で受け取り、円安の時期に換金することで利益を上乗せできる場合があります。
円高に転じる可能性もあるため慎重な運用が必要ですが、通貨の変動をうまく活用すれば、国内販売にはない収益チャンスを得られます。
国内市場依存リスクの分散
日本国内の人口減や経済動向だけに売上が左右されず、海外市場にも販路を持つことでリスク分散が可能です。
特定の国や地域に依存することなく、グローバルに複数の収益源を確保できれば、事業の安定性も高まります。
越境ECのデメリット・課題

魅力的な越境ECですが、国内ECよりも複雑な要素が多いのも事実です。
- 言語や文化の違い
- 高額な配送コストと長いリードタイム
- 各国の法規制や関税対応
- 不正取引やトラブルリスク
上記の課題を認識し、対策を講じることでスムーズな海外展開が可能になります。
それぞれ順番に解説していきます。
言語や文化の違い
海外ユーザーへの多言語対応や、現地の文化・商習慣を理解したプロモーションが必要です。
翻訳サービスや現地スタッフの採用、あるいはローカライズに強い制作会社と提携することで、コミュニケーションの壁を低くする工夫が不可欠です。
配送コストとリードタイムの増加
国際配送は送料が高額になりやすく、配達までに時間がかかります。
顧客が購入を躊躇しないよう、複数の配送オプションを用意したり、一定額以上の注文で送料を無料にするなどの工夫が求められます。
また、商品破損や紛失へのリスク対策として、梱包や追跡サービスを徹底しましょう。
各国の法規制・関税対応
輸出入に関する法律や関税制度は国ごとに異なり、販売できる商品の制限や特別な表示義務が存在する場合があります。
取り扱いアイテムによっては日本からの輸出が禁止・制限されているケースもあるため、JETRO(日本貿易振興機構)や専門コンサルを活用し、事前に調べておくことが重要です。
不正取引や返品トラブルのリスク
海外のクレジットカード不正利用や、長距離配送による返品・交換の煩雑化など、トラブルが発生する可能性は高まります。
セキュリティの高い決済代行を導入し、返品ポリシーを明確に記載して顧客に周知することで、ある程度リスクを抑えられるでしょう。
越境ECを始める前のチェックポイント

実際に越境ECを始める際は、以下のポイントを事前に確認しておくと、失敗リスクを下げることができます。
- 自社商品の海外適性の見極め
- ターゲット市場の需要調査
- 輸出入規制・関税の下調べ
- 物流・決済体制の整備
- 多言語サポート体制の確保
それぞれ順番に解説していきます。
自社商品の海外適性
自社の商品が海外で受け入れられるかどうか、言語や文化的背景を踏まえてリサーチしましょう。
特定の国では流行しやすいジャンルでも、別の国では需要がないこともあり得ます。
まずは市場規模や競合動向を把握することが大切です。
ターゲット市場の需要調査
単に人口が多い国を狙うだけでなく、購買力や嗜好、EC利用率などを総合的に検討します。
訪日観光客が多い国は、日本製品に強い関心を持っている傾向があるため、インバウンド需要と連携させる形で越境ECを展開する方法も有効です。
物流・決済の整備
海外配送の料金体系や保険、関税などをどう扱うか決めておきましょう。
費用負担を誰がするのか(顧客負担 or 事業者負担)、到着までの日数はどれくらいかなど、顧客が安心して注文できる環境整備が欠かせません。
決済に関しても多通貨対応やPayPalなどの導入を検討してください。
各国の法規制・規則の把握
国ごとの輸出入禁止品目や通関手続きの詳細を事前に調べ、違反しないように注意します。
食品や化粧品など、ジャンルによっては原産国証明や成分表示が必要になるケースもあります。
根拠のあいまいなまま販売を始めると、想定外のトラブルが起こりやすいので要注意です。
多言語サポート体制の構築
問い合わせ対応は越境ECの生命線です。
現地言語での質問やクレームに迅速に返信できないと、評価やリピート率に大きく影響します。
外部の翻訳サービスやBPOの活用も視野に入れ、顧客サポート力を強化しましょう。
越境ECの始め方・準備ステップ

越境ECを立ち上げるまでの一般的な流れを、段階的に押さえていきましょう。
- ターゲット国・地域の決定
- 販売プラットフォームの選択(モール型 or 自社サイト)
- サイト構築・商品ページの多言語化
- 国際配送・決済導入の検討
- 現地向けマーケティングと集客
- 受注・顧客対応・配送オペレーションの確立
最初から大規模に展開するのではなく、小規模からテストしながらノウハウを蓄積するほうが安全です。
各ステップ毎順番に解説していきます。
ステップ1:ターゲット国・地域の決定
まずはどの国や地域に注力するかを選びます。
自社商品の特性や需要、競合、物流コストなどを総合的に見極め、最も有望な国からスタートするとスムーズです。
ステップ2:販売プラットフォームの選択
モール型(AmazonグローバルやeBayなど)か、自社サイト型(Shopifyなど)かを選びます。
モール型は集客力が高い反面、競合も多く手数料がかかりやすい点に留意しましょう。
自社サイト型はブランド構築が容易ですが、集客・運営を自力で行う必要があります。
ステップ3:サイト構築・商品ページの多言語化
自社サイト型の場合は、多言語対応のプラットフォームや翻訳サービスを活用し、商品説明や決済ページを現地の言語でわかりやすく表記します。
モール型の場合も、画像やテキストをローカライズし、海外ユーザーが魅力を感じやすい情報設計を心がけてください。
ステップ4:国際配送・決済導入の検討
配送方法(EMS、国際宅急便、DHLなど)と決済手段(クレジットカード、PayPal、多通貨決済など)を準備します。
送料や到着期間、追跡サービスの有無などを明示し、顧客が安心して注文できるようにしましょう。
ステップ5:現地向けマーケティングと集客
海外SNSや広告プラットフォームを使って認知度を高めます。
現地のインフルエンサーとの協業や、セール・クーポン施策などを行うと効果的です。
ターゲット国の消費者が利用するメディアや検索エンジンでのプロモーションを意識しましょう。
ステップ6:受注・顧客対応・配送オペレーションの確立
販売を開始したら、商品が売れた際の在庫管理や発送手配、問い合わせ対応などを円滑に行う体制を構築します。
受注管理システムや外部のフルフィルメントサービスを活用すると、少ない人員でもスムーズに運用しやすくなります。
越境EC成功の事例

越境ECでは、大手だけでなく中小企業でも成功しているケースが多数あります。
ここでは下記の成功例を3つ紹介していきます。
- ヤーマン
- Tokyo Otaku Mode
- 中小菓子メーカー
これらの企業に共通するポイントは、現地ニーズを徹底的にリサーチし、文化や習慣に合わせたプロモーション・サービスを提供している点です。
海外ユーザーが求める“魅力”を的確にアピールすれば、日本発の商品であっても十分にグローバル市場で戦えます。
それぞれ順番に紹介していきます。
事例1:ヤーマン(美容家電)
中国向けの越境ECを積極的に推進し、Tmall Globalなどで売上を伸ばしています。
現地SNSを活用した情報発信やライブコマースを取り入れるなど、独自のマーケティング手法により顧客とのコミュニケーションを強化。
中国のECセールイベント時に爆発的な売上を記録するなど、越境ECがビジネス拡大の大きな原動力となりました。
事例2:Tokyo Otaku Mode(ホビー・アニメグッズ)
日本のアニメ・漫画関連商品を海外ファンに届けるECサイトとして注目を集めています。
SNSやコミュニティ活用により、世界各国にファンを獲得。
海外向けのサイト設計や送料軽減策など、顧客視点のサービス強化が功を奏しました。
事例3:中小菓子メーカーの海外展開
日本のお土産菓子を海外向けに販売する事例も成功例の一つです。
北海道など地域ブランドの魅力を打ち出し、英語や中国語で商品情報を発信。
少人数の運営体制でも翻訳サービスや物流代行を活用し、海外のリピーター顧客を増やすことに成功しています。
越境ECに役立つツール・サービス
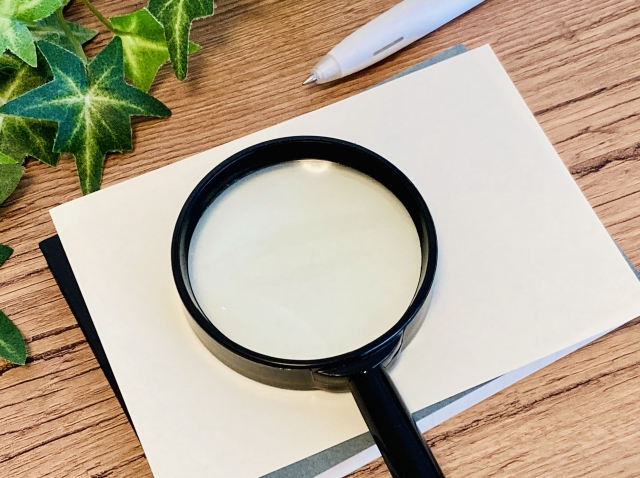
越境ECの運営をスムーズにするため、専門ツールや支援サービスを活用するのも賢い選択です。
自社のリソースだけでは難しい部分を外部の力でカバーすれば、スピード感を持って海外展開を進められます。
ここからは下記の4項目に分けて順番に解説していきます。
- 海外向けマーケットプレイス
- 自社EC構築サービス
- 多通貨決済・決済代行サービス
- 海外配送・物流サポート
海外向けマーケットプレイス
Amazonグローバル、eBay、Tmall Globalなどは、すでに世界各国のユーザー基盤が整っています。
出店登録と商品情報の多言語対応を行うだけで販売を始められるため、集客・決済に関わるインフラを活用しやすい点が魅力です。
自社EC構築サービス
Shopifyやfutureshopなど、多言語対応や海外決済をサポートするEC構築プラットフォームは、ゼロからサイトを開発する手間を省いてくれます。
拡張アプリで機能を追加できるため、成長に合わせて段階的にサイトを強化することも可能です。
多通貨決済・決済代行サービス
越境ECの肝となるのが、多通貨決済や国際ブランド対応です。
クレジットカード(Visa/Mastercardなど)のみならず、PayPalやUnionPay、Alipayなど地域特有の決済方法にも対応できるか確認しましょう。
SBペイメントサービスやヤマトフィナンシャルなど国内事業者向けの代行サービスも多数存在するため、比較検討が大切です。
海外配送・物流サポート
国際配送を担う業者(日本郵便のEMS、ヤマト運輸の国際宅急便、DHLなど)を使い分ければ、配送コストやスピードを最適化できます。
商品の重量・サイズ、目的地の距離に応じて複数のオプションを用意し、顧客のニーズに合わせることが重要です。
特に高額商品の場合は追跡や保険を付けると安心感を高められます。
まとめ

越境ECは、自社の商材を海外の巨大市場へ広げられる有力な戦略です。
国内市場だけでは得られない売上やブランド価値を獲得できる反面、言語や物流、法規制など国際ならではの課題へ備えなければなりません。
しかし、適切な調査と準備を行い、外部のサービスやツールを上手に活用すれば、EC初心者でも大きな成果を狙える分野です。
越境ECの仕組みと現地需要を理解したうえで、グローバルなビジネスチャンスを存分に活かしていきましょう。
ECサイトで売上をアップを成功させるためには、商品ターゲットや各ECモールのイベントキャンペーンに合わせた戦略や商品ページの作成が有効です。
サイバーレコードでは、商品ターゲットに合わせた戦略をたて、効果的な広告運用を行い、売上アップをサポートします。
ECでの成功に向けて、ぜひ弊社のサービスをご検討ください。お客様のニーズに合わせた柔軟な対応と、高品質なサービスをお約束致します。
\ 実績300社突破 !/